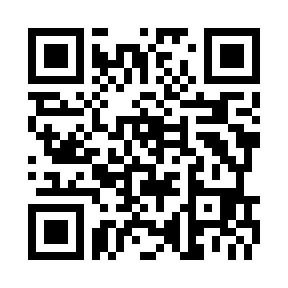2024年10月17日
ボーイスカウト浜松第6団のベンチャースカウト隊企画、ボーイスカウト隊ジョイント参加の「木曽駒ケ岳登山」の様子です。

ベンチャースカウトのS君が5月から企画したプログラムで、「後輩のスカウトと一緒に3000m級の山に登って、チームワークを高めたい」との目標で実施することになりました。

今回は、できるだけ公共交通を使うことが目標の一つでしたので、ボーイスカウト達はJR飯田線の中部天竜駅からの乗車となりました。

大きなザックを背負い、登山靴を履き、みんな装備はバッチです。

飯田線は単線なので、登りと下りの列車は途中の駅で交差するのです。反対側の列車が来るまで、待たなくてはいけません。

ボーイスカウト隊が電車に乗っているころ、前日から「駒ヶ根」に乗り込んでいたS君は駅で、みんなの到着を待っていました。彼は浜松駅から豊橋経由で「駒ヶ根」に来ていました。

この日はとても天気が良くて、これから始まる「山行」に期待が持てます。ただ天気が良いと言うことは、登山者や観光客も多いということで・・・。混雑が心配です。
10:53駒ヶ根駅にボーイスカウト隊が到着しベンチャーS君と合流。11:00のバスは見送り、11:30のバスに乗車となりました。

駒ヶ根駅からはバスで移動します。途中、自家用車で来た人を「菅の台駐車場」でぎゅうぎゅうになるまで乗せてから、コープウェイの起点となる「しらび平」まで進みます。

私たちの予想は的中、「駒ヶ根ロープウェイ」の発着点、「しらび平駅」は大混雑・・・。
登山者だけでなく、「千畳敷」までの団体観光客も溢れかえっていました。ロープウェイ乗車まで2時間30分待ちとのこと・・・。
もちろん1時間待ち程度は想定していたものの、想定をはるかに超える状況です。


結果十数台のロープウェイをその眼下から、見送ることになりました。

15:30になり、やっとロープウェイに乗車、標高2600mまで一気に上がります。

中間地点で登りと下りの車両が交差します。すっごいスピードです!

千畳敷に到着・・・。実証実験「ポテトチップス実験」は、この通り。各自が持ってきたポテチの袋はパンパンになってます。

ポテチ実験も早々に、登山準備にとりかかります。予定より2時間も経過していて、その後の予定が心配です

満を持して登山開始!急こう配の登山道を一気に登ります。ここでT隊長は息も絶え絶えに・・・。予定では千畳敷で高度に慣らしてから登山開始の予定でしたが・・・。

「乗越浄土」(のっこしじょうど)と呼ばれる、絶壁を横目に進みます。ここまで来ればあと一息です。


という訳で、最初の関門「宝剣岳した」に到着。
予定では宿泊予定の「宝剣山荘」に立ち寄り、大きな荷物を置いて身軽な状態で、この先の「中岳」を経由して、「木曽駒ケ岳山頂」までを往復する予定でしたが・・・。
計画者のS君とアドバイザーのSさんとの協議の末、それは明日にすることになりました。
予定が遅れてしまい、往復していたら日没になってしまうという結論に・・・

夕方、雲が下から上がってきました。周囲がゆっくりとベールに包まれてゆきます。

山小屋の夕食です。魚のフライにカラアゲ・きんちゃくの煮物・がんもどき・ごはんに。味噌汁・・・。山小屋の食事としては豪華です。

みんな明日に向けて英気を養います。

山小屋の食堂を借りて、明日の行動についてミーティングをしました。
今日行けなかった「中岳」と「木曽駒ケ岳登山」は明日の出発を1時間早めて対応することにしました。やはり「一番高いところに行きたい!」との気持ちが強かったのです。
コースと行動時間を確認してから、現地での時間短縮のために明日の課題の予習をすることになりました。山小屋の夜は早いのです。午後8時に消灯しました。

標高2870mのポテチの袋はますます膨らんで、とうとうこのような状態に。
開けるのが怖い!

深夜、窓から見た風景にびっくり!南東の伊那前岳ごしにオリオンが・・・。その美しさに思わずカメラを取り出して撮影。

翌朝5時に朝食をとり、30分後に出発の予定です。WBS隊長とK君、みんな準備に取り掛かります。

翌日はみんな元気いっぱいです。S君は予定表を手に気合十分。

出発まえに計画責任者のS君から、今日の行程とスケジュールについての説明が有りました。

気温はかなり下がっています。多分0~3℃くらいでは?遠方には「南アルプス」越しに「富士山」も臨めます。

こちらは八ヶ岳連峰。

最初の通過地点「中岳」に向います。

中岳に向かう途中で、日の出になりました。

なだらかな登りを15分で中岳に到着・・・。御岳山と眼下の雲海です。

向こうにみえるのが中央アルプスの最高峰「木曽駒ケ岳山頂」です。

せっかく登った高さを下ります。下に見えるのが「頂上山荘」テント泊の人たちはここにも・・・。

下って再び登って40分。木曽駒ケ岳頂上に到着。

木曽駒ケ岳山頂の社で、登山の安全を祈ります。

お約束の記念撮影です。「2956m木曽駒ケ岳」




頂上には「一等三角点」があります。



頂上は360°の大パノラマが臨めます。ここで方位角を使った課題に挑戦。S君が後輩のボーイスカウト達に課した問題です。御岳山・乗鞍岳・富士山と課題には事欠きません。
普段の訓練と昨晩の予習の成果で課題を早々に片付けて、次の目的地に向けて進みます。

出発早々、幸運が待っていました。


雷鳥です。花崗岩のまだら模様の保護色にうっかり見落してしまいそうです。
つがいの2羽がいました。足には赤い足冠が・・・。優しくも厳しい目をしています。ハイマツから顔を出してゆっくりと周囲を歩いていました。

のんびりとはしていられません。これからまだずっと先の「遭難記念碑」が、今回の登山の最大の目的地なのです。

木曽駒ケ岳山頂から尾根つたいに「農ヶ池」方向に進みます。

この頃には太陽もより強く輝き白い光に包まれます。

この先ずっと花崗岩がゴロゴロした「ガレ場」が続きます。これから先には観光客はいません。時々「将棋頭山」方面からの登山者と行き会うくらいです。
尾根の向こう側はさらに急な崖になっています。滑り落ちたら・・・。

そしてハイマツの中を一列になって進みます。周囲には人工物は一切なく、静寂だけがありました。聞こえるのはスカウトたちが地面を踏みしめる音とすり抜けるハイマツの枝が服に擦れる音だけです。

見晴らしの良い箇所で、アドバイザーのSさんから山の地形の生い立ちや、森林限界について、実際の地形が地図にどのように表現されているかの解説をいただきました。やっぱり現地に来て初めて知ることがたくさんありました。

美しい山々がずっとずっと続いています。

花崗岩の大岩の間を登ったり下ったりくぐったり・・・。とその時T隊長にアクシデントが発生!なんと靴のソールが外れてしまいましたよ!紐で縛って進むも、今後は逆の靴も同様に・・・。「何で今なの・・・!」どうなるT隊長・・・。山小屋付近ならまだ対応策はあるのですが、ここでは「帰る事も出来ないではあ~りませんか。」

目的達成のためには前に進むしかありません。

農ケ池方面に降りる分岐点を通り越し、さらに歩くこと20分・・・。やっとの思いで目的地「遭難記念碑」に到着。こんなところにこんなに大きな巨石があるのです。これは今から110年まえの大正2年8月に発生した遭難事故の碑なのです。
企画者のS君からの説明を後輩スカウトたちも真剣に聞いています。

私たちはこの登山を通じて、登山の魅力と共に「安全に登って無事に帰る」ことの重要性を心に刻みつけなければならないと痛感しました。

「聖職の碑」(せいしょくのいしぶみ)の教訓を胸に、一行は来た道を引き返し、分岐点から「農ケ池」に降りて行きます。
農ケ池は標高2650mにあり、千畳敷と同様に氷河期の氷河によって作られた谷に水がたまった池なのです。

ここで一行は、少し早めの昼食に・・・。山小屋で作ってもらったでっかいお弁当は、大盛り飯にたっぷりの焼肉です。こんなに大きな弁当!と思っていたらスカウトたちはベロリとたいらげてしまいましたよ。


帰りの時間が気になる一行はS君を先頭に再び標高2900mを目指して出発です。

途中の「駒飼いの池」付近から、急登になりハシゴを使って上に上に登ります。
この辺りで、グループは二つに分かれて行動することにしました。元気のよいスカウトたちとWBS隊長は先行してもらい、帰りのロープウェイの予約をしてもらうことにしました。昨日のように長時間待たされては、浜松へ今日中に帰れなくなってしまいます。

この辺りまでくれば、あと少しですが・・・。その少しがダラダラと長く感じます。
何とか最後の300mを登り切りました。

あとは千畳敷まで一気に下ります。この時点で時刻は12:00、下りのロープウェイに13:00までに乗ることができれば、予定通りの時間に帰着できそうです。
千畳敷で登山まえにお参りした祠に「無事に帰ることができました」とお礼参りを済ませ。
帰着の記念写真も、一時の休憩もままならず、特急で下りのロープウェイの列に並びました。後はそのままの流れでバスにて駒ヶ根駅までたどり着き・・・。予定通りの電車に乗ることができました。
大混雑で遅れたロープウェイ以外は、(途中の経路変更も含めて)全て完璧にS君の立てた計画通りに進み、全員がそれぞれの感動と思い出を心に無事に帰着できて素晴らしい「木曽駒ケ岳登山」となりました。
自宅で子供たちの無事の帰着を思って待つ父母みなさんの想いと、110年前の父母の想いとが重なって、よりいっそう安全に心掛けなくてはいけないと思う3日間でした。
Posted by ボーイスカウト浜松6団 at 14:34│Comments(0)